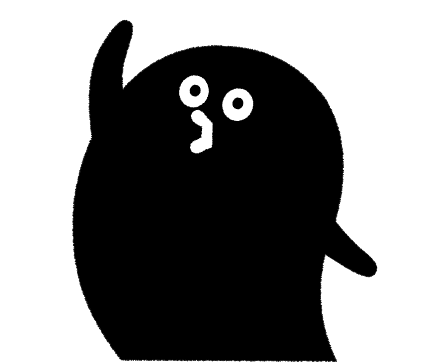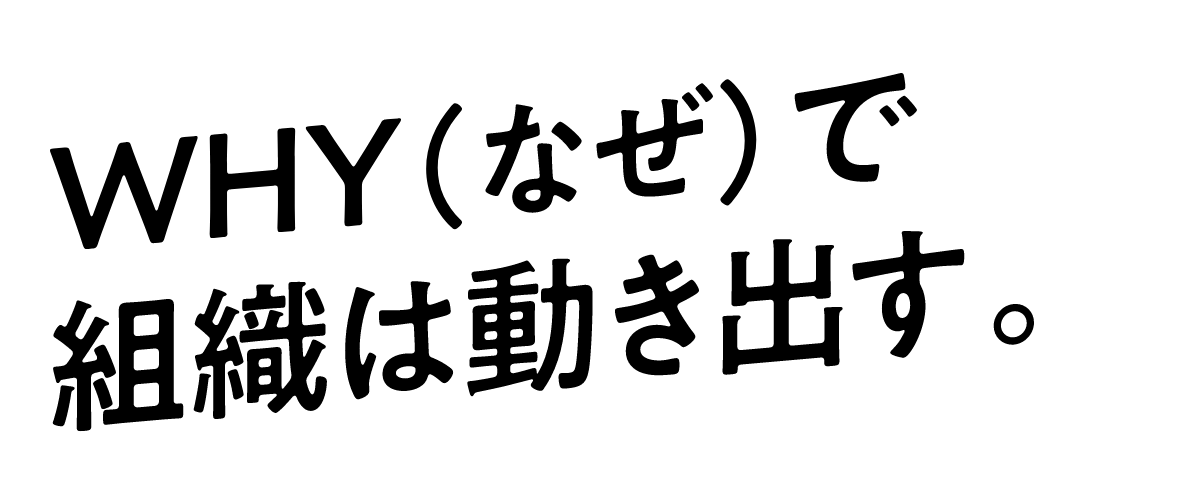
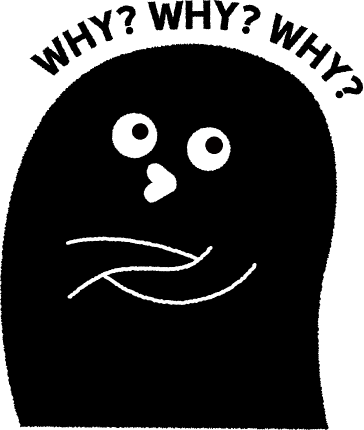
企業理念やミッション、ビジョンというのは必要なのでしょうか。
ある経営者は言います。
「理念?MVV?稼げる製品やサービスがあれば必要ないだろう」
それはある面では正しいです。
ニーズがある製品やサービスを正しく販売すれば、一定の売上や成長はついてきます。
そういった組織では経営者のカリスマや売れる製品・サービスが組織を束ねる力となっているため、そこまで理念は必要とされないでしょう。
しかし会社が成長していくと、社員が増えて社内の価値観が多様化する、また事業が多角化し何の会社かわからなくなる、といった局面が訪れます。
そんな時、社内では社員の当事者意識が徐々に低くなり、行動基準はバラバラ、指示待ちで仕事をこなし、社員間のコミュニケーションも希薄となりがちです。
その結果として売り上げは確保できているけれども伸び悩む、人材の育成がうまくいかない、離職率が高まるなどの課題が出てきます。
それらの解決のためにさまざまなルールや制度を作ったり、研修を行ってもうまくいきません。
そういった組織では、自分たちの事業(WHAT)のことや、どういう方法で(HOW)やり遂げるのかは理解していますが、
何のために(WHY)やっているのかわかっていません。
「いやいや、売上や利益のために仕事をしているんですよ」
という主張もありますが、利益は事業の「結果」であって、WHYにはなり得ないのです。
利益が最終的な目的になってしまうと、高給を取れる昇進が仕事の目的になってしまいますし、会社としても利益さえあげればコンプライアンスはどうでもいいという話になりかねません。
創意工夫しながら自律的に仕事と向き合うためには、高い目的意識が必要となります。そこでは「なぜ私たちが取り組む必要があるのか」「この仕事の先には何があるのか」を示すWHY(何のために)が必要なのです。
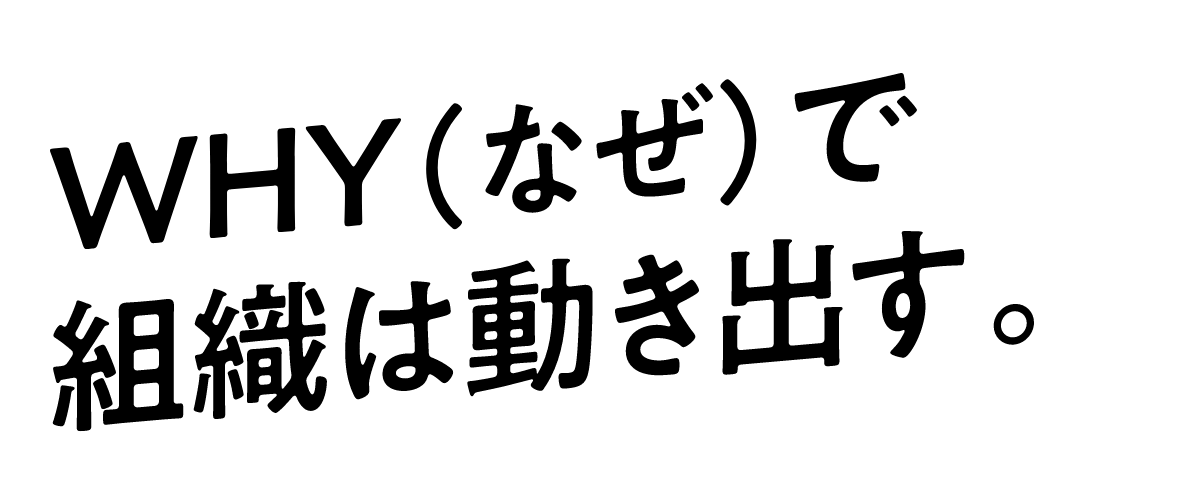
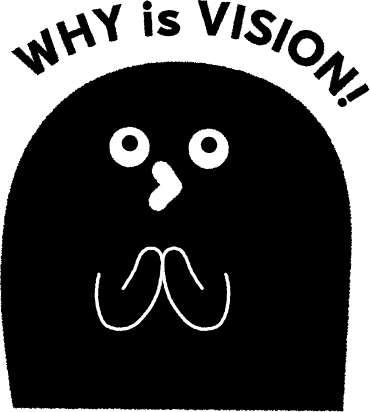
渡り鳥はなぜ、一糸乱れず目的地へ向かっていけるのか
『経営理念2.0』 の著者佐宗邦威は渡り鳥の群れを例にして、その群れが存続していくための条件は3つあるとしています。
- 方向感覚 これからの行き先が分かること
- 距離感覚 周囲の鳥に対して適切な距離を取ること
- 中心感覚 自分たちの群れの中心に向かうこと
渡り鳥の群れを会社と考えてみましょう。
- 方向感覚=未来の景色(ビジョン)
- 距離感覚=仲間と共有する価値観(バリュー )
- 中心感覚=集団が未来にわたってどんな存在であり続けるのかという意思(ミッション)
このうちWHYに相当するのが「未来の景色(ビジョン)」です。
どんな未来を自分たちが実現したいのかという「WHY(なぜ)」がモチベーションの根源となります。
WHYがわかっていなければ、どんなルールや制度も浸透しませんし、研修も腹落ちしないものとなるでしょう。
社員が増えることで経営者のカリスマが薄れてしまった、または売れる製品・サービスが組織を束ねる力とならなくなってしまったという場合、組織全体で同じ方向を向き進んでいくためには、やり方(HOW)を変えるのではなく、なぜ私たちはこの組織に属し、なぜこの事業を行っているのかを組織全体で共通の価値観とする必要があります。
理念では変えられないもの、変えることができるもの
私たちはすべての会社で理念が絶対必要とは思っていませんし、理念のかたちも決まったものではなく必要とする会社の数に応じてそれぞれだと考えます。
ビジネスを取り巻く環境は自分たちでは変えられませんが、自分たちの組織のありかたは変えられます。
そしてここまで読み進んだあなたは理念について考え直すタイミングなのかもしれません。
次のようなお悩みをお持ちではありませんか
- 何度言っても伝わらない
- 指示されたことしかやってくれない
- 共感してもらえるお客様をみつけたい
- 採算を考えずに物事を進める
- 判断基準、行動基準がバラバラで一体感がない
- 当事者意識が低く、他人のせいにばかりする